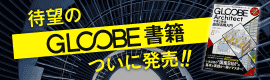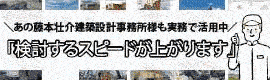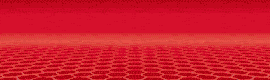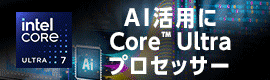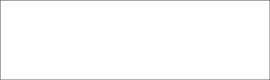![]()
原体験としての「箱の家」
2021.04.08
パラメトリック・ボイス
明治大学 / 川島範久建築設計事務所 川島 範久
私の建築家としての原体験のひとつに、前回のコラムでも紹介した難波和彦による「箱の家」
がある。
私は修士課程では環境系研究室に所属し、2005年~2007年の間、「箱の家シリーズ」を対象
に環境性能調査を行った。1995年から始まった「箱の家シリーズ」は、その頃既にNo.100を
超え、それまでの標準化、多様化の段階を経て、サステイナブル化を試みる段階にあった。
そこで、「箱の家」の環境性能の実測とシミュレーションを行い、現状を把握すると同時に、
どうすれば環境性能を向上をできるかを検証した。この調査については、住宅建築2007年
7月号(建築資料研究社)に寄稿した『エネルギー制御装置としての “箱の家” 』という記事で
詳しく報告したが、興味深かったのは、この研究調査を経て、「箱の家シリーズ」には、材料・
構法や設備計画における変化は多少あったものの、外観や空間構成には特に大きな変更はなかっ
たことだ。
このことは、環境的な視点から見直すことで新しい建築デザインが生まれると期待して環境系
に進んだ当時の私にとってはショッキングな出来事だったのであるが、そもそも「箱の家」の
外観や空間構成が変わるという期待が間違っていた、ということにしばらくして気が付いた。
つまり、「箱の家」の特徴である「深い庇を持つ南面大開口に面する吹抜を中心とする間仕切
壁のないガランドウな一室空間」といった構成は、日射制御や自然通風などのパッシブデザイ
ンの観点からははじめから優れていた、または、材料・構法・設備などの工夫を適切に行えば、
この構成でも十分な環境・エネルギー性能を実現可能である、ということなのだ。
ここに重要な事実が隠されている。
光・熱・風など、それぞれに特化し、コンピュータによる環境シミュレーションを用いるなど
して精緻な検証を行えば、それぞれの観点におけるベターな計画を導き出すことは可能だろう。
しかし、複数のパラメーターが統合された「箱の家」のシステムを維持できる範囲の計画の性
能が許容範囲内であるのだとすれば、その全体システムを崩してまでして採用するべき変更で
はないと判断することも適切と言えるだろう。また、難波が『新・住宅論』(2020年、左右
社)でも述べているように、「ある機能に特化した特異な形態は、はじめは意識にはたらきか
けるものの、時間の経過と共に異物と化してしまい、変化を受け入れにくいものになってしま
う」ことも考えると、フレキシビリティの確保のためには重要な判断でもある、と納得がいく。
また、一般論として、大開口は熱的に弱く、吹抜を持つ一室空間は空調制御が難しいと言われ
ている。環境実測やシミュレーションを行えば、その弱点は容易に指摘することができてしま
う。しかし、「箱の家」は、大開口と吹抜けを持つ一室空間により、内(家族)と外(都市)
に開かれ、自然(太陽や風)に開かれている。家族・都市・自然は他者であり、そのような
他者との関係性の中でこそ、人は変化していくことができる。このような変化を受け入れるこ
とができる住宅の構築こそが重要なのであり、その実現のために、「箱の家」にとっては、大
開口と一室空間はなくてはならない存在なのである。であれば、それを維持する前提で、必要
十分な環境・エネルギー性能を実現できるよう、材料・構法・設備計画を調整すれば良く、環
境シミュレーションなども活用して適切なエンジニアリングを行えば、それは可能なのである。
昨年(2020年)の秋、久しぶりに箱の家のオープンハウスに行った。このコロナ禍において、
箱の家の風通しの良いシンプルな設計は、実際の換気性能以上に暮らしに安心感を与えている
と感じた。この安心感は、「箱の家」はコンパクトな一室空間であり、大開口だけでなく全方
位に適切に窓が設けられていることで、どこにいても外部が感じられ、採光と通風を十分に行
うことができ、住まい手が自ら窓の開閉なども行える、といったことから来ているのだろう、
といった新たな発見があった。
「箱の家」は私にとって、建築家としての原体験であり、自分の居場所を測る定点である。

『箱の家164』(設計:難波和彦+界工作舎,2020年)写真©上田宏