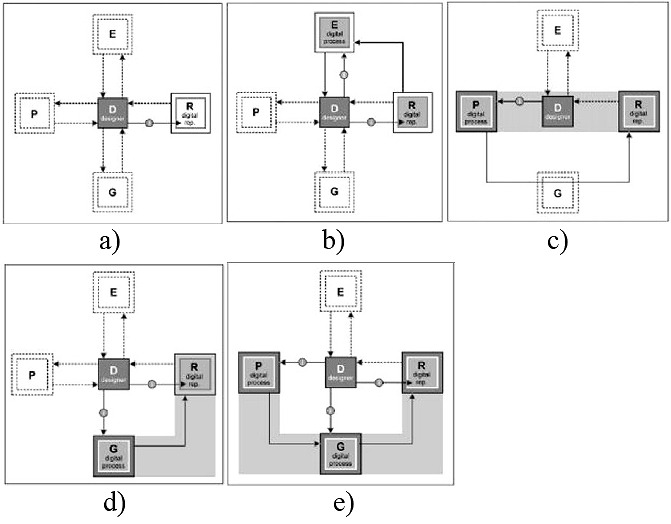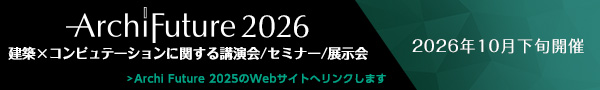![]()
BIMに心を開いていますか?
2025.03.18
パラメトリック・ボイス 熊本大学 大西 康伸
子どもたちはこんな風に世界を見てるんですね。
1月の底冷えする大きな体育館の真ん中で、ある保育士の口から独り言にも似た感想が漏れた。
ヘッドマウントディスプレイをかぶっているため表情はよくわからなかったが、声のトーンか
ら多少興奮気味であることが伝わってきた。
最近、BIMで設計したモデルを高品位なモデルとして即時的に(BIMのビューワーのように)
表示できるVRソフトが出現していることから、研究室が関わるデザインワークショップやプレ
ゼンテーションにおいて、VRを使う機会が多くなりつつある。そのような流れの中で、園長先
生をはじめ、保育士、栄養士の方々にお声がけし、VRを使って設計中の保育園を原寸大で歩き
回るワークショップを開催することになったのだが、せっかくなのでお手軽にできるVRならで
はの仕掛けが何かないものかと探していた。
実は、以前からヘッドマウントディスプレイをかぶってルームスケールでVRを体験すると、あ
る時は所狭しとコートを駆け回るNBAの選手のように、またある時は地を這う小さな虫のよう
に、何かの拍子に視点の高さが変わってしまうことがよくあった。
そのほとんどは、ヘッドマウントディスプレイを次の体験者に装着する際に起こるのだが、た
まに間違えて体験者がコントローラーのボタンやスティックに触れてしまうことで変わってし
まうこともある。
そんな、いよいよというところで気をくじかれるような経験から、逆に積極的に視点の高さを
変えることで、子どもになりきって空間を体験するのも新鮮で面白いかも、という考えに至っ
た。この試み、簡単にできそうという目論見もあり、安易な気持ちで通常の体験の最後に少し
だけやってみることにした。
いざ当日を迎え皆さんに一通り体験していただいた結果、図面やパースではよくわからなかっ
た(けれども、VRではよくわかった)という設計案に対する通常の意見が、当然のことながら
たくさん得られた。
だが一方で、子どもの視点を体験した際の驚きを帯びた感想が、これまた思ったよりもずっと
多かった。
子どもは年齢ごとに身長が大きく異なる。その体験を容易にするために、1歳から5歳まで年齢
ごとの平均的な目の高さを刻んだ身長計ならぬ眼高計を仮想世界の壁にところどころマッピン
グし、常に正確な高さが維持できるよう工夫した(出来合いのソフトを組み合わせて使うため
の工夫である)。
その甲斐あってか、私たちはいつも接しているから子どものことは理解しているとVR体験前は
知り顔だった体験者が、装着後には冒頭で述べたような熱いコメントを述べてくれた。
話は変わってその数週間後。今度はプロポーザルで選定された某市の地下通路デザインのプロ
ジェクトで、VRを用いる機会があった。
地下通路のような移動を伴う空間のデザイン評価には、自分の足で歩き回るルームスケールに
よるVRの体験がうってつけである。学識経験者から構成されるデザイン調整会議へのプレゼン
テーションのため、できるだけ大きな会議室をご準備いただくよう市にお願いし、何度もマッ
ピングやライティングをやり直したリアルなVRモデルを携えてプレゼンテーションに臨んだ。
しかし。
当日用意されていた会議室は模型さえも満足に置けない小さな部屋だったし、何よりデザイン
調整会議の委員の方々は、関西私大の教授であるT先生を除いて打ち合わせ中何度お勧めして
もヘッドマウントディスプレイを装着することはなかった。
よくあることだが、乗り物酔いが酷い人かもしれない。もしくは、装着した姿が近未来的すぎ
て人に見られるのが恥ずかしいのだろうか、いやいや、てんこ盛りのスケジュールを心配し会
議の時間が長引くのを気にしていたのか、ひょっとして自慢の髪型が崩れるのが嫌だったの
か?などと打ち合わせ終了後にプロポーザルチームのメンバーであれやこれやと想像してみた
が、どれもデザインを伝えるために頑張って用意したものを見てもらえない理由として納得で
きるものではなかった。
もし、ヘッドマウントディスプレイで見なくとも、自分の足で歩かなくとも、所詮プロジェク
ターに投影されたものと同じでしょ、だいたいわかりますよ、という考えであったとしたら、
それは非常に残念なことである。
これら2つの出来事から言えることは何だろうか。
大半の人々にとって、ヘッドマウントディスプレイをかぶったVR体験は未知の世界である。そ
の未知の世界にどのように接するかが、そこからの未来を左右する。訝りながらも体験し、少
しだけ異なる角度から世界を見る視点を獲得するか、体験の結果を決めつけ、今まで生きてき
た日常を繰り返すか。
BIMやそれにまつわる新たな技術によって、日々の仕事に絶え間ない変化がもたらされている。
その変化をどう受け取るか次第で、少しだけ自分の中で何かが変わり、その積み重ねがいつか
は大きな変化につながると信じている。
実は件の地下通路デザインのプレゼンテーションの際、デザインの意図が図面や透視図で上手
く伝わらなかったからか、当初は我々の提案の承認に暗雲が立ち込めた状態であった。しかし、
VRを体験したT先生が提案のよさを訥々と語り始め、そこから場の空気が一変し最終的に我々
の提案を継続的に発展させることになった。
いつだって変化の始まりは新しい技術に対して心を開く勇気ある者の行動である。今は皆が受
け入れなくとも、今はたった一人でも、何かが変わることが確かにある。
デジタルとは縁もゆかりもないT先生。そのような人と出会うことを、今後仕事の楽しみの
一つに追加しよう。