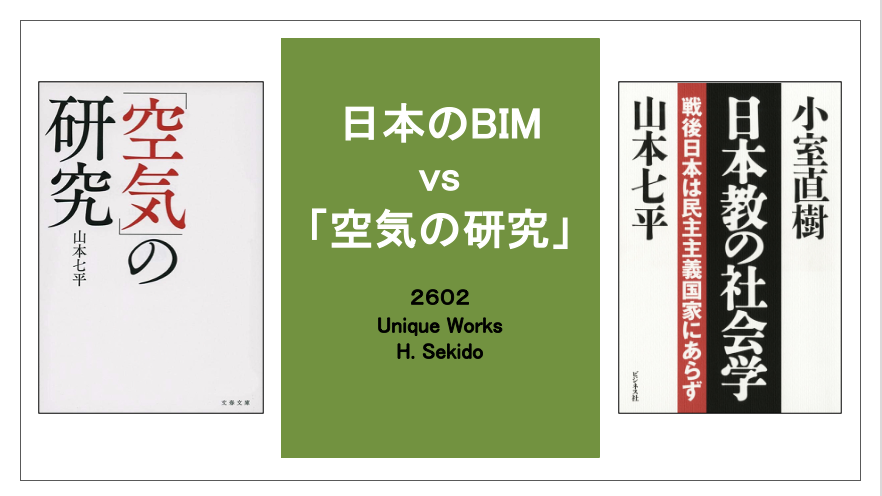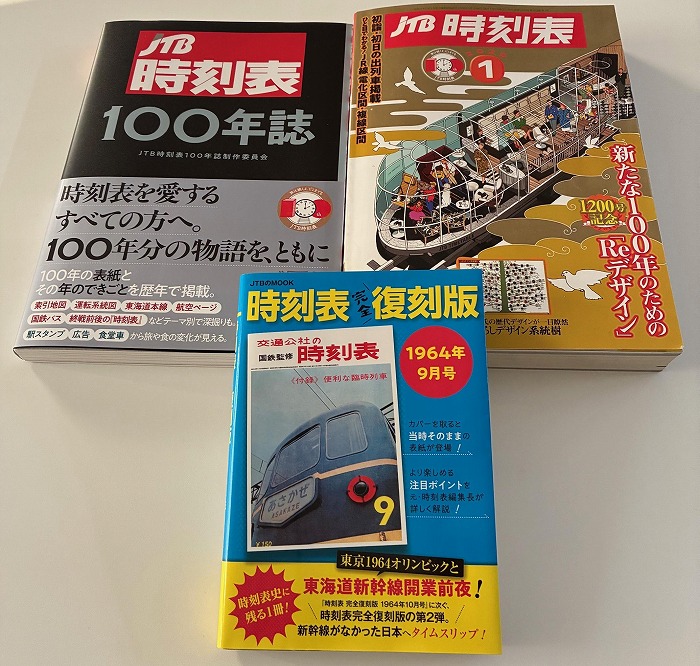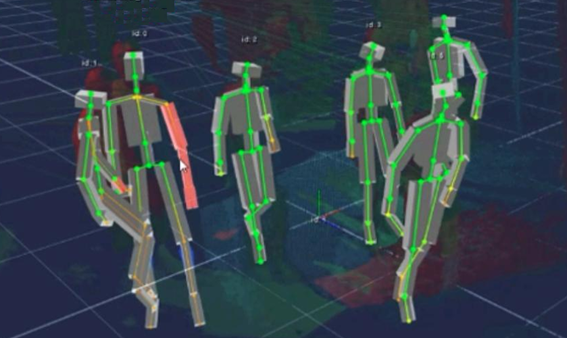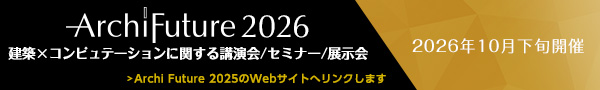![]()
BIMとAIと物語性
2025.08.21
パラメトリック・ボイス 熊本大学 大西 康伸
告白すると、正直、AIというものがあまり好きではない。
9月開催予定の日本建築学会大会での情報システム技術分野におけるAIをテーマとした論文数
は、AIのセッションが新設された2021年度の約4倍であり、その人気ぶりがうかがえる。論文
名をざっと眺めただけでも建築の様々な分野やフェーズに活用され始めていることがわかり、
まさに百花乱舞の様相を呈している。
昨今は空前のAIブームであるが、なんとなく距離を置いてそれを横目で見ている。意識はさほ
どしていないが、その恩恵を既に受けているだろうし、きっと将来はより大きな恩恵を受ける
ことになるものに対して、好きだ嫌いだと言っていられないのは十分承知している。だが、今
後化け物にもなりうるものに対する一抹の気持ち悪さがAIに対してはあり、古い人間だと言わ
れるかも知れないが、今のところそれを好意的に受け入れることはできていない。
BIMが建築の分野に入り込んできた時にはそんな風に感じなかったので、どうやら新しい技術
だからという理由で盲目的に毛嫌いしている訳ではないらしい。
AIに対して私が嫌悪感を持っていてもいなくても他の人にとっては別にどうでも良いことなの
だが、こうであってはならないという願いにも似た思いに、あることがきっかけで最近気が付
いた。
7月に入り、うだるような暑さが続いている。
数年前から日本建築学会作品選集の九州・沖縄ブロックの審査員を仰せつかっており、ここ数
年、この時期になると頬に日焼け止めを塗りたくって、建築作品の現地審査に臨んでいる。話
題の建築を隅々まで見ることができるばかりか、設計者や施主から直接説明を受けることので
きるまたとないチャンスである。現地審査ほど楽しいものはないと心の底から思っているし、
毎年この時期が来るのが待ち遠しい。
当該ブロックには離島がたくさんあり、毎年たいへん興味深い建築作品が現地審査の対象にな
る。幸運にも今年は奄美大島と沖縄の住宅を審査する機会を得て、2週連続で南の島に降り
立った。飛行機のタラップを降りた瞬間の、潮の香りを含んだ生暖かいあの風を全身で受けた
時の、例えようのない幸福感。それだけで現地審査への期待が否応なしに膨らんでしまう。
審査の詳細はここでは省略するが、2つの住宅に共通してプロジェクトに対する設計者の意志
や眼差しにただならぬ強さを感じ、そのことがとても印象的であった。
一方は、奄美の建築の伝統を革新し新たな伝統を築くという意志。当然、施主を含め誰もその
ようなことを依頼してはいないが、奄美に移住した若き建築家が、自身が奄美にいる意味を問
うために課した課題であった。もう一方は、幸せとは何かを建築を通して楽しく真剣に追い求
める施主夫婦へ向けられた眼差し。世界を股にかけて活躍する建築家としてあれやこれやと企
てたかったであろうが、敢えてそれを抑え愚直なほどに他人の人生を支えようとした。
無論、出来上がった建築の、ものとしての即物的な良さは素晴らしかったのだが、何より、建
築家が紡いだ物語にひどく心を打たれた。建築に限らず、この、いわゆる物語性なるものの強
弱が、つくり手を強くするだけでなく、つくり出されたものが時代を超えて評価され愛される
ためのエッセンスではないかと思う。
そのような人の意志や眼差しに対して、AIが誤った方向づけを行うことは断じてあってはなら
ないと思う。先ほどの願いにも似た思いとは、価値の基準を定める際に人がAIに惑わされない
ようにするためにどうすれば良いか、という問題提議に他ならない。もっとも、AIにそのつも
りはなく、単に人が浅はかなだけなのだが。うまく説明できないが、そのような意志や眼差し
を形成する段階やそれらに基づき人が何かを成すプロセスの中にAIがステルス的に深く入り込
み、人が知らず知らずのうちに良くない影響を受けてしまうことを、私は恐れている。
BIMも普及初期当時に、判で押したようなつまらない建築ばかりができるのではないかといっ
たような、良からぬ方向に導かれるという趣旨の議論があったが、AIほど巧妙に浸透するよう
な技術ではなかったし、プロセスの変化を強制するものでもあったので、人の側が気をつけて
いれば大した問題ではないと考えていた。
人がAIと適切な距離をとることができれば、誤った方向に行ってしまうことを防げるような気
がする。そのためには、人が意図通りに使いこなせる道具としてのAIの活用を含め、 AI自体
が自律した個体であると人が認識できる状況をつくることが重要である。
現在、研究室のTさんは大規模言語モデルを活用したAIを、過去のコラム「BIMと社内文化」
で紹介した維持管理支援システムに組み込み、日々報告される膨大なデータを分析し有益な情
報として提示することを試みている。この有益な、というところが味噌で、単にAIが導く何か
を有り難く頂戴するのではなく、維持管理そのものが将来どうあるべきかを強く望む確たる意
志や眼差しが人の側にあって、その思いの元でAIにより濾過された情報を研究室では有益と呼
ぶことにしている。
時代がAIをさらに進化させ、AIが物語性をも獲得しBIMと融合する時、建築設計における人の
存在意義は如何なるものになるだろうか。