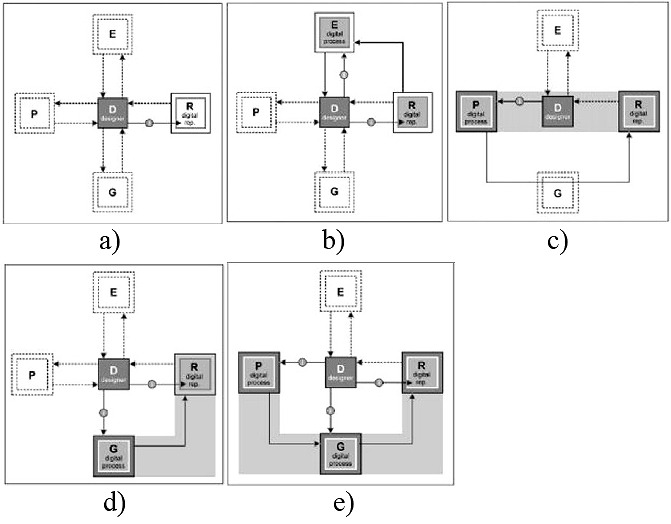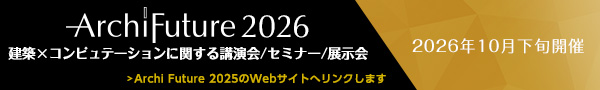![]()
冷蔵庫の残り物で作る建築
2024.06.25
パラメトリック・ボイス 髙木秀太事務所 髙木秀太

イラスト:溝口彩帆
幸せは冷蔵庫の残り物で作る料理にある
AKB48や乃木坂46のプロデューサーで有名な(いや、他にも有名な実績がたくさんありすぎる
んだけど)秋元康さん。3年前のインタビュー動画がとても印象的で、僕はこの動画を何度も
何度も繰り返し視聴してしまう。タイトルは「幸せは冷蔵庫の残り物で作る料理にある」。流
石は一世を風靡する作詞家さん、良いタイトルだなぁ。以下は「幸せ」に関する氏のインタ
ビューの引用。
| みんなよく自分に足りないものを欲しがりますよね。例えばお金、あるいは家、車、教養、 学歴、友達、いろんなものがあって、そういうものを手に入れたら幸せになれるかっていう と、、、きっと幸せになれない。つまりまた違う何かが足りなく感じるんじゃないかな、と 思うんですよね。 幸せっていうのは冷蔵庫の残り物で作る料理に似ていると思うんですよ。冷蔵庫の中を開け て作れない料理を考えたらきりがないじゃないですか。ね、例えば焼き豆腐がないからすき 焼きは作れないとか。ジャガイモがないからカレーが作れないとか。つまり、世界一大きな 冷蔵庫に世界中の食材を集めても作れない料理を考えたら何かあるわけですよね。で、何か 幸せっていうのをいつも、自分の不幸探しをするときりがないんだけども、冷蔵庫の残り物 でこれだったら何かこう「焼きそばもどき」は作れるねとか、これは「お好み焼きもどき」は 作れるとか。何かこう組み合わせで作れるものを考えたらすごい幸せだと思うんですよね。 Yahoo! JAPAN RED Chair「幸せは冷蔵庫の残り物で作る料理にある 秋元康という生き 方」より書き起こし(27:25 - 28:53) |
幸福論として分かりやすい、優れた比喩だと思う。僕はとても共感できる。人生において大切
なのは「ありあわせ」の豊かさを愛でられるかどうか。「てきとう」に「くみあわせ」るとい
う高度な営み、これこそが人間の「創造力(=クリエイティビティ)」と呼ばれる(他の生物には
持ち合わせない)極めて特殊で尊い能力なように思える。そう、それぞれの幸福というのは、そ
れぞれの人の内側にすでにきっと存在するものなんだ。
冷蔵庫幸福論は現代と相性が悪い、、、のか
一方で、この考え方に対して腑に落ちないヒトもいるはずで、それももちろん分かるような気
がする。幸せは内に無いものを外に求めてこそだ、という人はきっと一定数いるよね。それに、
この「冷蔵庫幸福論」、正直、現代(の日本)には相性が悪いと思ったりもするんだよね。だっ
てね、発達しすぎたコンピューター、スマホ、ネットワーク、、、これらはどうしたって冷蔵
庫の外の世界を見渡したくなる技術だと思うから。正確すぎるし、早すぎるし、便利すぎる
し、、、そして、視野が広くなりすぎる。理想の食材がほしいと思えばクリック一つで冷蔵庫
まで届けてくれるし、世界中の料理を調べることもできる。くわえて(これが特に厄介だと思
うんだけど)誰かがもっと美味しそうなものを食べていることが簡単に分かってしまうし、誰
かに改善のダメ出しだって受けやすい。「あの食材が〇〇g無いと理想の料理は作れない」、
「この手順のあとにこの器具でこう加工しないとダメ」、「もっと美味しくて美しいものが世
の中には存在する」、「そんな料理で満足しているの」、、、まさに「きりがない」無いもの
ねだり。何が言いたいかというと、つまり、デジタル技術の発達は「冷蔵庫の残り物で作る料
理」では満足しにくい世界を作ってしまった、そんなふうに思えてしまうんだ。
神経質な建築設計
最近、建築設計に関しても同じようなジレンマがあるように思える。正確無比なデジタル技術
で作られた図面や3Dモデルという「遊びのない絶対的なレシピ」による、足りないもの探しと
ミスが許されない工程。そして、さまざまな基準で建物(の計画)が正確に測られ、既存の世界
中の建物と比較されていく。「あと〇〇%空調効率を上げるほうが良い」、「木材は〇〇トン
使ったほうが良い」、、、。デジタルテクノロジーが設計者を神経質にさせている。日本の建
設業界はこの神経質さで堅実に建物のクオリティを上げていったからこそ発展した今日がある
わけで、その歴史や文化を否定することなんてことはもちろんしないのだけれど、、、。
だけどね、本当は建築設計は「冷蔵庫の残り物で作る料理」みたいな豊かさを本質的には持っ
ているはずなんだよね。もともと、建物は限られた敷地や限られた予算、そして、限られた資
材をつかって作る「ありあわせの料理」のようなもの。地産の建材で作られた土着的な建物や
自然の理に逆らわない仮設的な住居、世界を見渡せばそんな内なる豊かさをもって作られた建
物がたくさんある。最近僕はつくづく思うんだ、もっと肩肘の張らない、まさに「冷蔵庫の残
り物で作るような建物」の作り方があるんじゃあないのかって。いや、それは「作り方」(=メ
ソッド)ではなくて「心の持ち方」(=マインド)なのかも知れない。デジタル技術は本当に良く
出来た「世界一大きな冷蔵庫」なのかも知れないけれど、でも時には神経質になりやすい知性
を休めることも必要なのかもしれない。僕は建築設計の業界で生きるプログラマーを10年以上
続けてきたけれど、ここのところ、いろいろなことに対して思考がデジタライズされすぎたと
いう反省がある。ものづくりをするうえでの豊かな思想や発想、そんな大切ななにか(の一部)
を広大なデジタルの海原に落っことしてきてしまったような感覚さえ覚えるんだ。

イラスト:溝口彩帆
ありあわせの豊かさ―「ブリコラージュ」
元の話題に戻って。秋元康さんは間違いなく哲学者クロード・レヴィ=ストロースの名著「野
生の思考」(みずほ書房, 1976年)を読んでいる、あるいは、内容を知っているんじゃあないか
な。少なくとも僕はすぐに連想した。同書には「ありあわせの豊かさ」を表現する「ブリコ
ラージュ」というキーワードが出てくるんだけど、まさにこういう考え方を表す単語なんだ。
「ブリコラージュは、理論や設計図に基づいて物を作る「設計」とは対照的なもので、その場
で手に入るものを寄せ集め、それらを部品として何が作れるか試行錯誤しながら、最終的に新
しい物を作ることである。」(Wikipedia 2024年3月24日 (日) 03:08版 より)。じつは建築設
計に関する論考でも昔から良く出てくる単語なんだけど、さて、いよいよもう一度、新デジタ
ル時代の「ブリコラージュ」を考えなおす時に来ているんじゃないかな、と僕は思うんだ。資
源枯渇、少子化問題、働き手不足、市場縮小、、、どんどん「足りなくなっていく世界」で、
僕たちはデジタルテクノロジーといっしょに建築設計の幸福をどう考えていくべきだろうか。
もしかしたら、その答えの一端は僕らの内側にこそ存在しているのかも知れないね。

イラスト:溝口彩帆