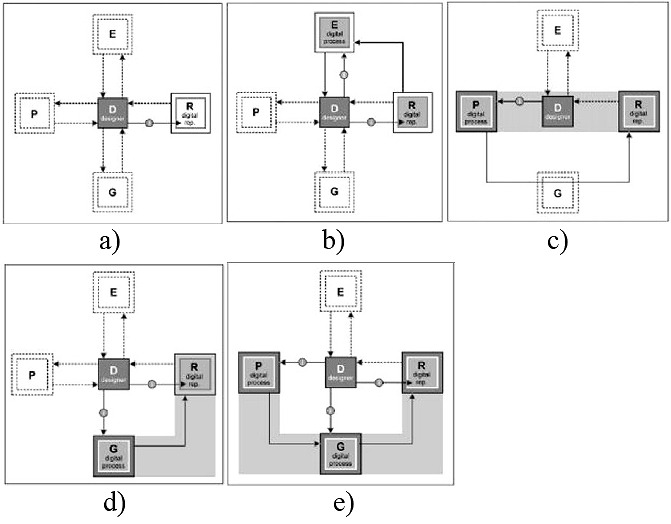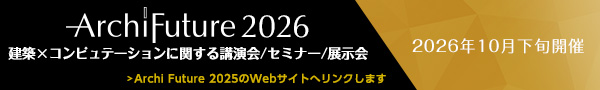![]()
ARが拡張現実であるためには
2025.09.11
パラメトリック・ボイス
東京大学 高木 真太郎
ここ数年、AR(拡張現実)という言葉を耳にする機会が増えました。これは、私が豊田研で
特任研究員をしているからかもしれませんが、産業用途からエンターテインメントまで、多く
の領域で導入が進められているように感じます。エンタメコンテンツを入り口としてARに触
れるたことがある人も多いのではないでしょうか。スマートフォンを片手に街を歩き、画面越
しにポケモンを愛でた経験を持つ人は少なくないでしょう。こうしたARコンテンツは多くが
スマホやタブレットといったデバイスを使用したものですが、より没入的に、より直感的に、
現実とデジタルの境目が曖昧になるAR体験を可能にするのがHMD(ヘッドマウントディスプ
レイ)です。昨今、様々なHMDが登場しており、高度なAR体験を日常の多くの場面で体験で
きる未来はそう遠くはないように思えます。
ビデオ透過型と光学透過型
先ほど例に挙げたHMDは、大きく「ビデオ透過型(VST)」と「光学透過型(OST)」に分
けられます。ビデオ透過型は、カメラで捉えた現実世界の映像にCGを重ね合わせ、その合成
映像をディスプレイに映す方式です。これに対して光学透過型は、透明なレンズを通じて現実
世界を直接見ながら、そこにCGを投影する仕組みです。前者は「現実を映像として再構成す
る」アプローチ、後者は「現実をそのまま基盤とする」アプローチともいえるでしょう。
近年では、Meta Quest 3やApple Vision Proが登場するなど、ビデオ透過型が注目を浴びて
います。カメラ映像とデジタルコンテンツをピクセル単位で精緻に重ね合わせることで、オ
クルージョン(手前と奥の関係性)や光の演出を自然に扱えるため、没入感という点で、大き
な魅力を持っています。
ARの定義とビデオ透過型の課題
ここで、そもそも「AR(拡張現実)とは何か」を考えたいと思います。ARの定義は1997年にRonald T. Azumaが示したものが有名です。その定義では、次の三条件が揃っていることと
されています。
①現実と仮想要素を組み合わせること
②リアルタイムでの相互作用が可能なこと
③三次元的な位置の整合性が取れていること
ただ私はもう一つ重要な項目があると考えています。それは「現実空間が主であること」で
す。なぜならARはAugmented Reality、すなわち現実を拡張する技術だからです。拡張の対
象はあくまで「現実」であり、ARを使う人が知覚する現実世界は、使っていない人が知覚す
るそれと同じであるべきだと考えます。
この観点に立つと、ビデオ透過型にはいくつかの課題が浮かび上がります。最大の特徴である、
体験者が「カメラを通した現実世界」を見ることによるものです。例えば電源が切れたり、機
器に不具合が生じたりした瞬間、ユーザーの視界は黒い画面へと転じ現実世界そのものが遮断
されてしまいます。
また、私たちが見る映像は処理済みの映像であり、それが「本当にその場の現実」であるかど
うかを検証する事は困難です。遅延や歪み程度あれば、HMDを着けたままでも検証できると
思いますが、意図的な加工が加わっていた場合などは、それを見抜くには究極的にはデバイス
を外すしかありません。
そしてもうひとつは身体感覚です。人間の視野は水平方向で約200度、垂直方向で約130度に
及びますが、ビデオ透過型のHMDの多くはそれより狭い視野角しか提供できません。そのた
め、周辺視野が制限され、人は普段よりも大きく首を振り、余分な動きを強いられます。
建築・都市スケールで考えるAR
この課題は、建築や都市といったスケールでのAR利用を考えると一層明確になります。たと
えば災害時、避難経路をARで提示する場面を想像してみてください。光学透過型であれば、
もし突然HMDが壊れても現実の建物や街路は見えたままです。しかしビデオ透過型では、視界
そのものが突然途絶えてしまい危険に晒されます。
さらに、生活の中での活用を考えると、カメラを通した現実世界は体験者に安心感を与えられ
るでしょうか。例えば、最近の自動車ではカメラ映像を用いたバックモニターが普及していま
すが、フロントガラスが全てバックモニターのようになったらどうでしょうか、自動車の信頼
性を持ってしても、それで走行するのにはまだ不安を感じませんか。ARも同様に、生活の様々
な場面で活用するには常に現実世界が見えている安心感が必要なのだと思います。
これからのAR
もちろん、ビデオ透過型の魅力を否定するつもりはありません。没入感という一点において、
それは素晴らしい体験を提供します。エンターテインメントや教育、医療などで大きな役割を
担うでしょう。しかし「日常に寄り添うAR」という観点では、私は光学透過型HMDの未来に
強い可能性を感じています。実際、ここ最近ではXREALをはじめとするスマートグラスの開発
が盛んです。現実を直接見ながら、そこに必要な情報だけを重ねるAR体験の発展も近いので
はないでしょうか。
最後に、このコラムは東京大学生産技術研究所豊田研究室メンバーが持ち回りで執筆させてい
ただいているコラムの一つです。他にも様々なテーマのコラムがたくさんありますので、ぜひ
ご覧ください(他のコラムはこちらから)。

高木 真太郎 氏 東京大学生産技術研究所 特任研究員