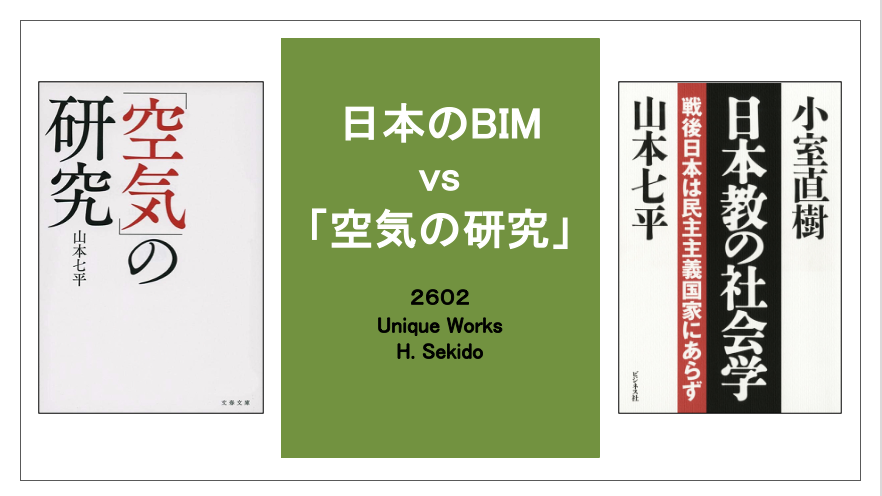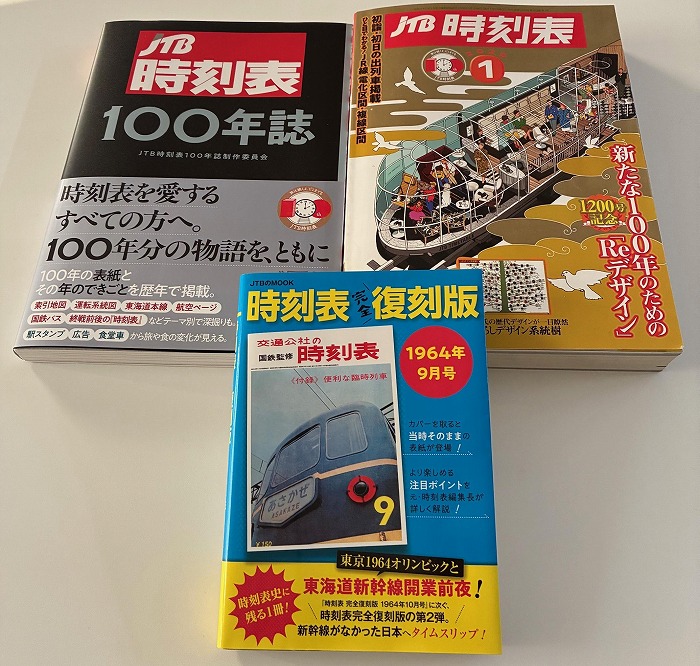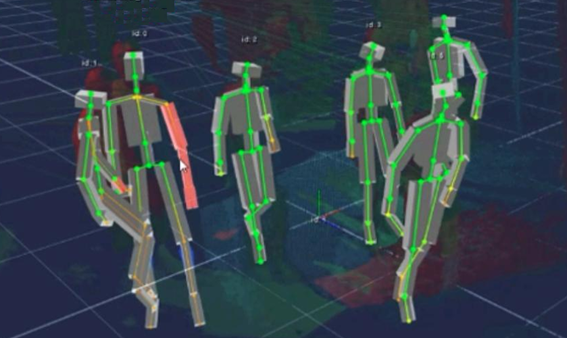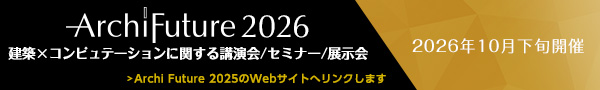![]()
デジタルもアナログも
-ブリキとキャベツから発想したテーブルデザイン
2025.11.04
ArchiFuture's Eye 日建設計 山梨知彦

写真01:完成したテーブル。脚の部分が、キャベツから発想した構造になっている。ブリキ板
の厚みは0.15mm。テーブルの上に置いてあるのは、デザインの発想につながったキャベツの
3Dモデルや、プログラミングにより作り出した3Dモデルなど。
振り返ってみると、2023年の生成AI元年以来、設計や創造のプロセスは、様々なところで変化
している気がする。直感的な印象になってしまうが、2009年のBIM元年ごろの議論がデジタル
か?/アナログか?の二者択一を迫ってくるようなものであったことに比べると、今の状況は、
「アナログ」と「デジタル」の領域が、一つの思考空間の中で連続的に扱えるようになりつつ
あるような感触を受けている。あえて言うと、素材に直接触れる手の感覚と、生成AIの能力が
補完し合いながら、無理なく新たなかたちを導いているように感じている。
こんな時代において、設計の現場で我々はどう振る舞うべきか──。その問いへの一つの応答
として、私たちは今回、テーブルという極めてシンプルな構造体をめぐる小さな実験を通して、
アナログとデジタルの往復運動をたどってみた。
日本製鉄さんが主催するプロジェクト「ブリキのリデザイン展2025」に参加する機会をいた
だいた。テーマは「薄い金属板を使って新しいプロジェクトをデザインすること」。この
テーマに対して私たちは、建築家らしいアプローチとして、プロダクトそのものを設計するの
ではなく、それが置かれる背景や場の“舞台”となる存在──つまり、プロダクトを支える
「器」としての空間や構造に目を向けたいと考えた。そこで提案したのが、一つの展示空間を
支える「テーブル」という装置だった。それは単なる展示台ではなく、素材そのものの可能性
を空間的に引き出すための「舞台」として構想された。このプロジェクトを進めるにあたって、
現在日常の業務で使用している生成AIを無理なく、手慣れた範囲で使ってみることにより、
変わりつつある生成AIを使ったデザインプロセスを客観視してみたいと考えた。
デザインに先立ち、最初に日本製鉄さんから、小さなブリキ板のサンプルをいただいた。試し
に曲げてみると、驚くほど簡単に曲がる。その変形は塑性変形させなくても、弾性変形域内で
もかなり自在に形が作れるという柔軟性を持っていた。そして何より驚いたのが、その軽さ
だった。鉄というと重く硬いイメージがあるが、このサンプルはわずか0.1mmの厚みの鉄板
は、まるで紙のように軽い。どれでいて、ブリキ板の薄板の表面は金属特有の光沢を帯び、曲
げた際に生まれる曲線はとても美しく見えた。これは素材というよりも、形態を引き出すため
の「メディア」だと直感した。

写真02:完成したテーブルの脚を上からみたところ。ひだをつくり曲面にすることにより
合剛性が生まれると同時に、ブリキ板に金属光沢も生まれる。
ただし、それだけでは全貌は見えてこない。より大きなスケールで試すため、高さ90センチ、
長さ10メートルほどのロール材を提供してもらい、実際に手で折り曲げてみた。すると、素材
の大きさが変わることで、必要な力やひだの大きさも変化することに気づいた。人間の腕力と
いう“生身の限界”と鉄板の物性との相互作用によって、ある範囲に収束する自然なパターンが
生まれる。これは言い換えれば、人間の身体(腕力)と鉄板の薄さと大きさがパラメータとな
り、実はひだの大きさはある寸法と曲線に収束するのだ。“アナログなアルゴリズム”により、
誰が曲げても、ある幅の中にピッチが収まるという現象が再現されるのだ。

写真03:完成したテーブルの脚と天板のアクリル板を下から見上げたところ。人間の手でひだ
をつくると、生まれる曲面の大きさはほぼ一定になることがわかる。
こうした「手で考えるプロセス」と並行して、論理的な視点からもテーブルの形状を追求して
みた。造形の論理的なヒントとなったのは、野菜の構造だった。当初はキャベツの断面に惹か
れた。キャベツの断面を観察してみると、外周は比較的な球形をしているが、その球状の内側
に複雑な曲面が幾重にも折り重なり、内側に向かって秩序あるかたちが生成されていることが
わかる。ここには何らかの生成アルゴリズムが存在するように思われた。
この仮説を検証するためには、生成AIは現在最強のツールであろう。生成AIと音声で話しあう
と、直ぐにこの現象が「結球」と呼ばれるものであることを教えてくれた。これを画像検索に
かけるとで、キャベツや白菜の美しい断面画像を多数収集・検討できた。次は、この構造体を
実際にモデル化して眺めてみたいと思い、実際にキャベツを切ってみて、3Dスキャンしてみた
のだが、想像していた以上に固体差が大きく、手元にあるキャベツを切ったものからは、美し
い3次元モデルはつくれなかった。そこで今回は、写真から3次元データを生成(偽造)する
サービスを使ってみた。これは、デザイン作業中に、学術的に正確なモデルは必要がないが、
それらしい三次元デーダが必要(背景や点景などのモデリング)な際に多用しているものだ。
これにインターネット上で見つけた理想的なキャベツの断面写真を入力することで、1分ほどで
精巧な3Dモデルを自動生成した。このデータを元に3Dプリンターで造形したモデルは、造形
イメージの共有や検討の場面で大きな助けとなったし、あまりにも出来が良いので、最終的に
はテーブルの上に配置するコンセプト説明用にも使うことになった。
キャベツの生成原理のプログラム化も試みてみたが、中々ゴールが見えなかった。そんな状況
の中で、さらに生成AIと会話していくと、同じ「結球」でも、今回のテーブルに向いているの
は、キャベツのそれではなく、むしろ白菜のそれだとわかってきた(笑)。白菜は、立体として
は、球ではなく円筒形の構造をしており、縦断面では長方形、水平断面では円形をしている。
キャベツのような三次局面からなる構造体をブリキ板からつくるには、プレス機などによる塑
性変形が必要になる。ところが白菜であれば、二次曲面であるため、ブリキ板を弾性変形させ
るだけで簡単につくること出来る。このかたちは、今回のようなテーブル脚の構造にぴったり
だった。つまり、人間の手でブリキ板を曲げて“ひだ”をつくり、その集積によって、結果的に
“白菜的構造”が立ち上げることが出来るのだ。これこそが、このプロジェクトで目指したテー
ブルの「かたち」であると確信して、モックアップを完成させた。

写真04:完成したテーブルの全景。脚はロール状に巻きあげることでコンパクトになるため、
仮設の大テーブルとして使うことが出来そうだ。ちなみに、今回はモックアップということ
で、ブリキ板相互は、強力磁石を使って固定してある。
こうした一連の体験を通じて、私は強く思った。設計という行為は、アナログかデジタルかと
いう問題ではない。むしろ、アナログだからこそ気づけることがあり、デジタルによってその
気づきを概念化・構造化できるという、相補的なプロセスが存在する。手で素材を確かめ、身
体感覚から発見し、それをAIとともに検証・展開する。その往復運動の中で設計が立ち上がっ
ていく。そして、少し前までは夢物語のようだったこうしたデザインプロセスが、いまや簡単
な操作で、日常的なツールとして扱える時代になった。これは改めて驚くべきことである。
若い建築家やデザイナーは、すでにこうした環境に自然に慣れ親しんでいるだろう。AIやデジ
タルツールを使いこなし、アナログな手作業との往復を当たり前のように行っているかもしれ
ない。
しかし一方で、まだ多くのデザイナーが、こうした技術やプロセスに対して距離を感じている
のも現実ではなかろうか。大切なのは、それを忌避せず、両者を行き来しながら設計を進めて
いく柔軟さではないだろうか。アナログとデジタルの間を行き来するプロトタイピングの繰り
返しこそが、設計を豊かにする鍵になる。
(ちなみにこの文章は、原稿を書こうと思ったところ、パーキンソン病の都合で手が動かなく
なったため、ChatGPTに私自身がヒアリングしてもらい、その結果をもとにChatGPTにまとめ
てもらったものである。私は口頭による指示はしたが、筆記具やキーボードには一切触れるこ
となく、この原稿を書き上げた。こうしたことが既に楽にできる時代になったことは、とても
喜ばしいことである。)
我々が進むべきは、「アナログかデジタルか」ではなく、「アナログもデジタルも」だろう。
- イベント名: DESIGNART TOKYO 2025
- 展示タイトル: ブリキのリデザイン展2025
- 会期: 2025年10月31日(金)〜11月9日(日)
- 会場: 日本橋兜町/景色 KESHIKI
- 出展: ブリキのミライ
- 告知動画(クリックするとYouTubeへリンクします)