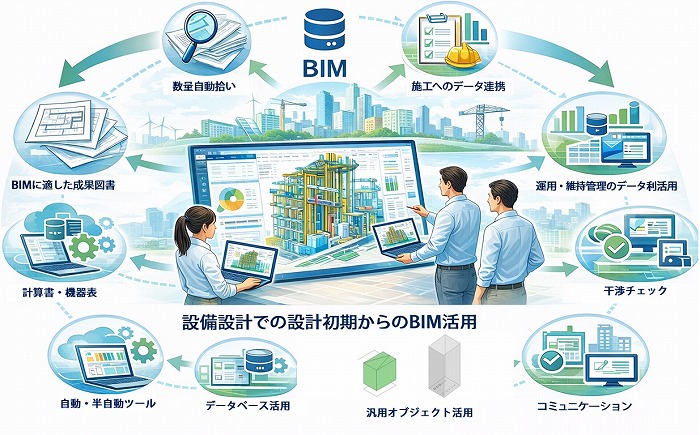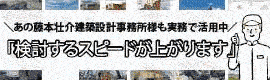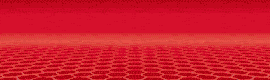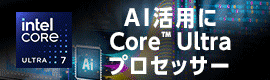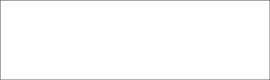![]()
耳なし芳一と記号接地問題
2017.05.30
ArchiFuture's Eye ノイズ 豊田啓介
耳なし芳一という話は、なんとも忘れがたい、強烈な印象を残す怪談だ。
深夜のあばら家、墨と毛筆で生身の肌に書かれたお経、目の前にいる幽霊に体をなめまわす
ように探索される恐怖、こちらは知覚できるが相手は知覚できない不安定な非対称性、いつ
知覚されるかわからないという緊張感、致命的ではないとはいえ最後に体の一部を持ってい
かれるという勝ちとも負けとも言えない絶妙な余韻と僧の今後の余生に残るであろう悲哀
等々、なんとも構図としてもビジュアルとしても精緻でかつ艶めかしく、強烈な余韻を残す
話だと思う。全身に直に文字を書くという行為自体が、意味論としても感性としても非常に
センセーショナルで、このイメージはさまざまなアートや映画作品のインスピレーションと
なってきた。
ただ、イメージの妖艶さ、物語の文学的洗練はひとまず置いておくとして、僕はこの話には
子供のころから引っかかっていることがある。
一体幽霊にはどこから耳が見えて、どこから消えていたのか。
耳と体の間には、誰もが納得する明確な物理的境界線はない。仮に体の部位的な属性(耳、
首、手など)ごとにお経の効果があるのだとすれば、一体どの線から先を耳と定義するの
か、その境界線はどこなのか。明確なのかぼやけていたのか。もしお経の個々の文字が効力
の単位とするのなら、個々の文字が持ちうる影響範囲はどの程度で、それはどう定義される
のか。アウトライン化されたフォント境界ベクトルからのオフセット?文字の面密度重心か
らの半径?そうした距離は皮膚という二次曲面上の表面距離で定義されるのそれともデカル
ト空間座標上を最短距離で貫く直線距離なのか?そもそもこうしたイメージはいかにも
NURBS曲面上に文字が展開されているイメージだが、耳の切断面はソリッドモデルのよう
に塞がれているのかそれともNURBS面の裏側が見えるのか?影響範囲の定義が二次元か三
次元かは置いておいて、そのオフセット距離や半径はどうやって決まるのか?お坊さんの法
力が数値化されるのか?お坊さんの法力がすごければ体に一文字書くだけでスカッドミサイ
ルの射程距離のように全体がカバーされて消えることもあるし、小僧で射程が短ければ文字
の周辺2㎜だけとかいう法力の各を数値化する指標があるのか?だとすると、文字の粗密や
法力の射程距離によっては耳以外にも飛び地としての残余の皮膚があちこちに見えている可
能性あるんじゃないのか(文字とはそもそも疎であることを前提にするから、間に大小さま
ざまな隙間が存在する)?などなど。
物語の概念からするとどうでもいい話なのだけれど、僕はこの辺のどうでもいい点がどうし
ても気になってしまった。もちろん子供の時にイラストレーターはなかったし、アウトライ
ン化とオフセットなんていう概念は知らなったけれど、今の言葉で説明すれば、そういう違
和感だ。
僕は子供のころから地図が大好きで、家ではひたすら地図を描いていたし、社会の授業中は
ただひたすら地図帳を眺めていた、そして地図帳の巻末などにある世界のなんとかランキン
グ的な資料のうち、海岸線の国別比較統計に関しても同じようなことを考えていた覚えがあ
る。すなわち日本は海岸線が国土に対して長く、アメリカよりもずっと小さいのに海岸線の
長さは日本のほうがずっと長いのだという。でも、海岸線の長さってどうやって定義される
のか。地図帳の線にそってぐるぐる定規を当てていくのか。ではどのスケールの地図帳でそ
れをするのか。縮尺が上がれば上がるほど細かいジェスチャーは多くなり、総延長はいくら
でも増えそうに見える。さらに地図でなく実際の砂浜には岩場があり、岩場にはくぼみがあ
り、くぼみの間には砂があり、砂の間には表面張力で水が入り込み、ボール状である個々の
砂粒は表面張力で水が被るからどの水平面で切るかによって断面形状も相応程度に異なる。
そもそも分子レベルではトポロジカルな境界すら定義のしようがなく、かつそれよりはるか
に大きなスケールで波なるものが常時そんな条件を際限なく無力化している。砂粒周りの周
長を追っていったら、フラクタル海岸の総延長なんてどんな国でもすぐに無限大に発散して
しまうんじゃないか、等々。
今考えれば、ある程度比較の手法として現実的に割り切るという意味で、もうちょっと大人
な方法があるとも思うが、当時は地図帳にそんな順位が出ていること自体がどうにも納得が
いかず、先生に食って掛かったりしたこともある。
こういう厳密性を科学的に追い始めるとすぐに分子や原子、さらには素粒子という世界にた
どり着き、それらの存在や定義、認識論みたいな話、我々が日常スケールで常識とする物理
世界とは異なる系(例えば量子論の世界のような)の常識が徐々に入ってこざるを得ない。
しかし僕らは日常という十分に実効的なスケールや解像度の範囲もしくは単位の中で生活し
ているわけで、コーヒーを飲むのにいちいち量子論的影響とその可能性の総和などを気にし
ている暇も必要もない。そうした日常とは別のスケール、非日常的解像度ではじめて顕在化
するような科学的厳密さは、知識や哲学的認識の上では存在しても、現実世界では無視する
べきであるということがほとんどだ。前提からして圧倒的に実学である建築設計の実務など
というのは、特にそうした科学的・哲学的厳密性にこだわることに、現実的に大した意味は
ない。
いや、ごく最近までなかったはずだ。
例えばピクサーのアニメーションでは、顔の表情を豊かにコントロールするため、NURBS
曲面は多くのUVサブサーフェスに区画されている。それら個々の区画ごとに、多様な変形
パラメーターが定義され、それらの連続的な合成により、そうした区画やパラメーターが認
識不可能なくらいに自然でシームレスな一つの表情を作り出す。そうした表情は見る人の中
に感情や共感を誘発し、そこにはデジタル技術ならではの新しいコミュニケーションの手法
が生まれつつあると言える。最近のモーションキャプチャによる動画生成などは、そうした
技術の気の遠くなるような積み重ねのたまものだ。その中で彼らは、例えば耳と頭、ホホと
顎との間に厳密な境界を引くことができるし、パラメーターをどういう割合で動かすと楽し
そうに見えるかをデータ化し定式化することができる。デザインの過程でそうした厳密な分
割や定義、要素化という問いを徹底的に経た先に、新しいタイプの創発的表現の可能性をつ
くりだしたのだと言える。例えばピクサーが耳なし芳一の映画をつくるなら、空中に浮いて
いる耳の切断面をどう見せるか、会議をしていろいろ試して、何らかの決定をして厳密なモ
デリングを行わなければならない(そのうちそんな作業もAIがするようになるかもしれない
けれど)。その厳密な決定という段階は、こうした手法で先へ進むうえで避けようのないプ
ロセスだ。もはやそこに社会的曖昧性という逃げは許されないし、感覚は感覚のままデザイ
ンするというざっくりとした常識は通らなくなりつつある。
これは建築でも同様だ。良いか悪いかは別として、現代のデジタルツールをプラットフォー
ムとする以上、これまでは曖昧なままでよかった異なるスケールやレイヤ、機能に属する
個々の部位や属性を、厳密に区画して定義し、かつそれぞれに固有のパラメーターや評価関
数、動きのアルゴリズムをこれまた厳密に定義してやらなければ事物は設計できなくなって
いる。こうした手法は、最終的な形態そのものだけでなくそのプロセスやアルゴリズムにお
いても同様で、そうした分野でパラメーターやジオメトリ特性などを、これまでのような曖
昧さで誤魔化すことは不可能だ。設計という環境が、さらには日常という空間がデジタル化
し、そのプラットフォーム上で現実の世界とやり取りをするためには、そうした曖昧さは少
なくとも一度、厳密さを経由しないわけにはいかなくなっている。そして、これは制限では
なくて可能性だ。
例えばAIの世界に、記号接地問題という議論がある。ここで深入りするつもりはないが、デ
ジタルデータという形式を経ることでしか現実世界を認識することが(少なくとも現時点の
技術と人間の認識力とのバランスの中では)できないいわゆるAIに、いかに重層的なスケー
ルでメタな単位の意味性(たとえばこれが「耳」であるという認識)を持たせるかという問
題は、現在のところ「人間が定義を与える」以外の方法では難しい(とされている)。耳な
し芳一の物語では、芳一も僧侶も幽霊も、そしてそれを読む読者も、当然のように記号接地
問題を気にすることはない。ところが、これをデジタルプラットフォームを経由して映像化
する、共有可能なコンテンツにする、デザインとして実装するとなると、既に環境はそんな
曖昧さは許してくれなくなっている。その定義を人間がするかAIがするかは置いておくとし
て、我々の社会はおしなべてそういう解像度を避けられない段階に入っている。
僕は全てがデジタルで、認識として厳密である世界を礼賛するつもりはない。むしろ最近は
いろんなメディアで、デジタル技術がもたらす可能性は今よりもっと曖昧な認識、インタラ
クション、コントロールを可能にする世界で実装されると言うようにしている。僕はこの、
これまで曖昧でよかった認識世界に一度厳密さを導入しないとその先の「新しい」曖昧さに
到達できないという話は矛盾などではなく、社会がプラットフォームを変えるにあたって通
らざるを得ない思春期のようなものだと考えていて、全てを一様に厳密に定義してみる、そ
の過程で認識論や構造に関する概念の再構築なども必要に応じて行うことで、その定義や技
術、情報量の爆発が人間の認知や意識下でのコントロールの限界を超えて「あいまい」な現
れ方で「十分有効な」制御をする以外になくなるとき、はじめてデジタル技術が自然とシー
ムレスになる非機械論的な世界観が、我々に備わるのだろうと期待している。
デジタルが、アナログがといった不毛な二項対立でものごとを論じる傾向はまだ多い。でも
その先により高レベルでの融合があるのだと考えると、そんな対立の図式は大して意味のな
いものに思える。携帯電話のGPS測位技術も、日常で我々が感知する必要のない相対性理論
で位置補正をしない限り今使っているような精度が出ることはない。既に現在の日常には、
そうした厳密な解像度への問いとその回答なしには成立し得ない事象が、ほとんど数え上げ
られないほどに満ちている。それらをただユーザーとして享受することに何も問題はない
し、十分に楽しい世界だとは思う。ただ、何かを創造すること、新しい価値に認識可能な形
を与えることを生業とする身として、何も知らないまま結果としての曖昧さを、その曖昧さ
の新しい質を理解せずに享受するよりは、徹底的に厳密さへの問いと技術、自らに求められ
る環世界の再構築という多大な労働を突き詰め乗り越えることで初めて見える世界の先に、
あらためて登場する新しい曖昧さ、価値体系、新しい自然(のようなもの)を感知し、そこ
に働きかける術を持っているほうが、幾分か面白そうには思える。