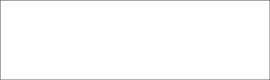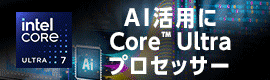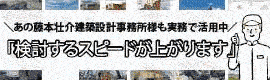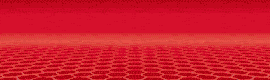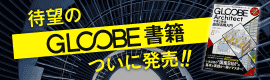![]()
サイバネティクス全史―人類は思考するマシンに
何を夢見たのか
2018.02.15
パラメトリック・ボイス 東京大学 木内俊克

サイバネティクス全史「アシュビーのホメオスタット装置」の挿絵 撮影:木内俊克
せっかくの3連休だったので、溜まっている仕事の解消に励む傍ら、一冊本を読み切ることに
した。サイバーセキュリティーを専門とするイギリスの社会科学者トマス・リッド原著、松浦
俊輔訳の「サイバネティクス全史―人類は思考するマシンに何を夢見たのか」(原題:Rise
of the Machines)だ。これが予想以上に面白く、ここ半年ばかり考えてきてずっと取りまと
めたかった、筆者が取り組んだパブリックスペースのプロジェクト「オブジェクトディスコ」
で意識化しつつあったデザインの方法論整理にも思いがけずヒントを与えてくれた。
公共空間における私たちの視点は常に複数性(すれ違いと言ってもいい)をはらんでいること、
それでも私たちは公共空間を共有しそこに価値を見出す*1こと、またその視点を編集できれば
物理的に街を変えなくとも都市デザインと呼べる介入になる*2だろうこと、そしてその鍵を情
報技術が担っているだろうこと。コラムを書きはじめてから、これらの切り口で関連するもの
ごとを探してはメモするようになったが、この「サイバネティクス全史」は、そうした筆者の
興味のそもそもの前提となる歴史的な史実を総ざらいしているものだった。
サイバーという言葉は、サイバースペース、サイバー攻撃、サイボーグといったように、一般
に日本では他の言葉に接頭辞的に付加されて「インターネットが形成する情報空間(サイバー
スペース)に関連した、の意」を指したものとして用いられている(出典:デジタル大辞泉
"小学館")。本書では、そうした一般化した「サイバー」という語がいつどのように形成され
たかを歴史的に遡り丁寧に解きほぐしつつ、結果「サイバネティクス」とは何であるか、現代
においてどんな意味を持つのかが、そのメカニズムと影響の緻密な描写をとおして技術的、
社会的、文化的に記述されている。
サイバネティクスの起源は、本書によれば第二次大戦だ。戦闘機の性能が飛躍的に向上し、搭
載された機械が実行されたアクションに対してどのような結果が伴ったかを確認しては微調整
するというフィードバック制御を組み込んだ自動操縦補助が実装されていなければ、その操作
自体がままならいレベルに到達していた。またそれら戦闘機を迎撃する防空システムには、高
度なマイクロ波のレーダーが対象の戦闘機を追尾し、発射された砲弾は十分に対象に接近した
かどうかを検知して自ら爆発する、やはりフィードバック制御機構が求められた。後にサイバ
ネティクスという語の直接の生みの親になったノーバート・ウィーナーは、こうしたフィード
バックループの全盛期と並走する形で飛行中のパイロットの心理的ストレス下での行動予測を
研究していた。そして1948年に制御・フィードバック・人とマシンの合体を核とした概念が
まとめられた「サイバネティクス」がウィーナーにより出版された。
その起源を当時の最先端の軍事産業にもつサイバネティクスは、絶えることのない先へ先へと
いう新規性への欲望を駆り立てる。本書では、そのサイバネティクスが常に時代の先端を指し
示すユートピアとその終末を予感させるディストピアを生産しながら、その間を往還運動し続
けていった様が詳細に描かれる。サイバネティクスは、あらゆる人工のシステムの自動化を志
向し、生物体を機械により拡張し、カウンターカルチャーを誘発し、仮想空間を囲い込み、サ
イファーパンクを生んできた。
しかし、サイバーという概念がここまで広く普及してきたのは、そうした近未来的な駆動力の
みによるのかというと、それだけではなさそうであることが実に面白いところだ。サイバネ
ティクスは日常とは切り離された最先端の宇宙開発や軍需産業だけを変えたのでなく、どうや
ら私たちの日常に身体にどっぷりと染み込み、私たちの自らの身体を捉える視点そのものを変
えてしまったようであることも本書では指摘されている。
サイバネティクスの特質をもう一度振り返れば、制御・フィードバック・人とマシンの合体の
3つの概念が挙げられるが、比較的抽象性の高い動作に関するサイバネティクスの特質を捉え
た制御・フィードバックに対し、人とマシンの合体はリッドの言葉を借りれば、より「想像力
をかきたてた」ものだった。
1949年、イギリス西部のグロスター近郊にあるバーンウッドという村の精神病院に勤務してい
たロス・アシュビーがつくったホメオスタットという装置も、何かを入力したら何かが出力さ
れ、その蓄積に「学習」が観察されるという点でその装置が「思考している」ことを、フィー
ドバックの概念から紐解いたものだったが、その発表の場にいあわせたベイトソンにより、
そのブラックボックスを「生態系が示すもののような学習と同じ」であることも指摘された。
そして、その「学習」する系は生物体であり環境でもあって、その間に固定した境界を引くこ
とはできない、というアシュビーが提出した理論的な枠組みは熱をもって受容された。アシュ
ビーの主張はウィーナーによっても強く支持され、大脳から見れば「体の一部」も「身体外に
あるもの」も等しく環境なのであり、生物体と環境は主題に応じてどこにでも系の境界線を引
きうる、元来連続的な存在だという議論にも接続された(そしてその実証実験も一部行われた
ようだ)。
ポストモダン思想の潮流の中であらわれたダナ・ハラウェイが、「私たちはみんなサイボーグ
だ」と説いたことは、こうした視点の積極的な拡張であり、事実社会で醸成された概念の根幹
をついていたと言えそうだ。サイバネティクスが人間とはなんであるかを逆照射した。サイ
ボーグはハラウェイにとっては「突破された境界」であり、「体とマシン、人間と人間でない
もの、心と体、あるいは自然と文化、男と女…」の二元論に固定された様々な境界は実際は絶
え間ないフィードバックループの中で常に変動し続けているというのが彼女の発言の骨子だっ
たが、その意味で元来人間はサイボーグだったのであり、サイバネティクスの到来によりよう
やくサイボーグとしての人間の存在が明らかになったという議論だ。
あらためて筆者が冒頭であげていた問題意識をサイバネティクス的に言い換えれば、それは公
共空間を媒介に身体から環境まで連続した情報の入出力の系をどう組み立てうるか、といった
問いに言い換えられそうだが、こうしてハラウェイまで読み進めてくると、筆者の問題意識は
ほとんど80年代までに一度は歴史の俎上にあがっていた議論であることが再認識できる。では
2018年現在の立ち位置からそこに何を付け足せるのか。
本書の最終章は、ある程度その問いに示唆的な一節を残して閉じられている。それはサイバネ
ティクスの歴史的に通底して見出せるパターンについてであり、サイバネティクスは、
―サイバーはスピリチュアルであり、科学がトーテムを生み、マシンが化身(アバター)
になったこと、サイバーは神話であり信仰であるということ
―ポジティブとネガティブが共存する矛盾をはらむものであり、神話がその矛盾を包みこ
んでいること
―技術の速度は常に神話を上回り神話を書き換えてきたということ
―新語に対する欲求が並外れて強いこと
―アイロニーであること。私たちに似せて作られたとしても、間違うことがあるのは私た
ちの方だけだということ
といったパターンを持っていることが指摘されている。そして、確固としたことは、人間とそ
の環境はすべてが入力であり出力でもあって、急速に、完全に、不可避的に変化するというこ
とだけであり、そして「未来学者はもちろん、いつも未来について間違っていたわけではない
が、ほとんどいつも速さ、規模、形については間違っていた。今も相変わらずそうだ。」と結
び、最後に「ウィーナーはパイロットと乗っている飛行機というサイバネティクス装置が、ス
トレスのかかる中で20秒後にどのようにふるまうかを予想して失敗した」ことを思い起こし、
それを思い出すことは有益だとしている。
であれば、やれることは絞られているように感じられる。サイバネティクスはその名で呼ばれ
続けていくのかはともかく、これからも作動し続けるのだろうし、それを書き換えていくのは
おそらくこれからもとどまることのない技術だ。そして私たちはどう自覚していようともサイ
ボーグであり続けるし、その系の中で入出力をかけ続けていくしかない。しかし、リッドが指
し示すように、私たちは常に間違え続けてきたし、逆に間違えることができ、急速に、完全に、
不可避的に進行する変化について自覚的であることもできる。
冒頭で触れた「オブジェクトディスコ」 の設計作業は(詳細については、新建築2017年10月
に詳しいので同紙面を参照されたい)、それ自体はきわめてあいまいな方法化への意志の萌芽
のようなものでしかなかったが、あらためて本著を下敷きにそこでの仮説をブラッシュアップ
すれば、私たちが自分たちの身体であり環境をデザインしていくということは、
1. 「サイボーグ」としての設計チームや施主、その他関係者の身体であり環境の反復的な
入出力を構成している、なるべく汎用性の高いどこにでもある日常の構成要素を一つ
ひとつ抽出し(その方法は写真データでもテキストデータでも音声でもよいかもしれ
ない)、
2. 都市の時空間に広がる膨大な概念の束との間にある距離や接続性を具体的に測り、
3. その場と来るべき時間における身体や環境の構成要素が接続する意味/非意味のポテ
ンシャルをなるべく多様な系に開くこと、
4. そこに技術を媒介させ「急速に、完全に、不可避的に」ドライブさせること、
5. 結果、私たちの「間違える」能力を積極的に増幅すること、
であり、そうすることで技術の速度がいずれ私たちの神話を書き換える瞬間まで私たちはその
「間違い」の織り成す文化を生産し続けることができ、来るべき書き換えを自覚的に乗り越え
て次のイテレーションに乗り換えていくこともできようになるのではないか。
仮説は仮説でしかなく、むろん実践と検証が待たれている。そしてその為には技術の波を乗り
こなすサーフボードとしての身体と環境のデザインツールが必須だ。歴史がそれを照らし出て
いる。
いまもいくつかのプロジェクトが動いていて、現実的な制約の中で大きなシナリオを描くこと
は大変なのだけど、そのデザインツールの手続きを細かくつくり込んでは検証していくことが
鍵になるんだろうとあらためて手綱をしめ直す。よい休日だった。
*1 上妻世海氏(以下、上妻氏)は「芸術作品における“魅惑の形式”のための試論」
(artscape 2016年10月15日号フォーカス掲載)において、人と事物の関わりについて、「孤
立し隠遁している複数の時間軸が無関係のまま世界に存在している。…僕たちはこれからもほ
とんどすべての時間軸に無関心なまま暮らしていくだろう。しかし、ときに、偶然に、あるい
は何かの意図に寄り添うかたちで、僕たちは魅惑されてしまう。…他者の、モノの、作品の時
間軸を狂おしいほど求める。非対称なまま…それは分かり合えないモノ同士が、分かり合えな
いまま、不安定な約束を結ぶことである。そして、異なる2つの時間軸の“間”に共通の時間を
仮設することである。」と述べ、こうした「魅惑」を積極的に発生させることに芸術の役割を
見出している。本稿では、都市は上妻氏の指摘する人々の無関心と魅惑が同時共存する場とし
て想定されている。
*2 上妻氏は「制作を媒介に神話的世界へ。上妻世海インタビュー(後編)」(美術手
帖.com INTERVIEW - 2017.4.11)において、貨幣システムや政府という仕組みがあくまで
国民の合意の上に成り立っている取り決めでしかないという意味で、小説や映画と同一平面上
にある虚構であると述べた上で、「虚構を生活のレベルで機能させるためには非常に多くの労
力が必要」であり、現実とは圧倒的な労力が担保する「虚構がもつ実在性(リアリティ)の濃
度」が高められた状態を指すと指摘している。さらに「日常のなかで虚構の実在性を成立させ
ている構造を学習し、異なる仕方で組織化し、制度を構築することで、別の虚構にリアリティ
を持たせることができる」とも述べている。
また氏は「“東京の〈際〉”を制作せよ──関係の写像を超えて“未来”を拡張するためのプログ
ラム」(10+1 2017年9月特集)においてはより具体的に、「“東京”を各々の体験によって生
じるものとして見る場合、それは各々がその街の人々と結んだ関係の束である…そして、異な
る関係への媒介を制作することは関係の束としての都市開発を意味している。…情報社会にお
ける都市開発とは、「関係の媒介としての場」を「都市」の内部構造に組み込むことである」
と述べており、明示的に新しい都市開発の可能性を示唆している。