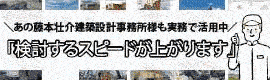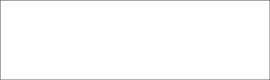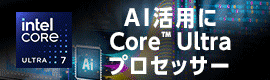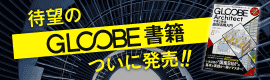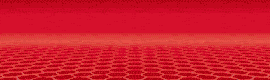![]()
ネットワークへ
2021.03.02
パラメトリック・ボイス 木内建築計画事務所 木内俊克
2017年からArchiFuture Webのコラムを執筆してきた。断続的に計23本、年に6本弱という
ペースで、筆者の関心のおもむくまま自由に自分の考えをスケッチする場をいただいてきたが、
実は考えあって今回を最終回とし、これにて一旦コラム掲載に区切りをつけたいというわがま
まをArchiFuture Web 編集部に了承いただいた。右往左往するテキストを、それでも毎度掲載
し続けて下さったArchiFuture Web 編集部にはあらためてこの場を借りて感謝申し上げたい。
筆者が編集チームとして携わった「建築情報学へ」の出版から2か月が経ち、4月からついに建
築情報学会も本格的に始動する。いま何を考え、実践していきたいのか。あらためてゼロから
仕切り直す機会として以下にメモを記し、最後のコラムに代えたい。
初回のコラムで、Diller Scofidio + RenfroのBad Pressについて書いた。90年代のプロジェク
トだが、日常に何気なく存在するYシャツの「フォーマルな」折り目が輸送効率を最大化する
経済的な四角形に基づいていることに対する批判的なオルタナティブとして、ねじり、ひねら
れて、「たたまれた」シャツの折り目を提示する(エリザベス・ディラー氏によるBad Press
の1994年のレクチャー)というアプローチは今でも色あせない鮮やかさをもって迫ってくる。
どこにでも情報は埋め込まれている、そして、それを読み換えては別の解釈を与えていく新し
い視点さえ見い出せれば、身の回りのものごとや、ひいては都市がいまこの瞬間から180度
ひっくり返る可能性がある。そんな思いを鼓舞される。
2017年に書いたコラムでは次のような問題意識にも言及した。
「…公共空間から誰が何を読み取っているかは、思いの他共有されていて、思いの他異
なるものに違いないはずだ。そして、だとすれば筆者は…訪れる一人ひとりの人たちの
場の読み取り方に大いに興味があるしできる限りその情報をインプットしたいとも思う。
そこでのあらゆる人の読み取りの自由を最大限確保しながら、まだ存在していない読み
取りを誘発し、かつその場を共有される場として調停すること。そのどれも成立してし
かるべきものだとも思う。」
公共空間には、常に複数、多数の視点が作動している。そのずれが交錯する場こそが公共であ
り、そこに差異があること自体を価値とし、その差異を享受しにおとずれる場所が都市ではな
かったか。また同じ関心の延長上で、2018年にデジタルアーカイブについて書いたコラムで、
こんなメモも記した。
「Aという概念を調べるとき、キーワードを含む複数の検索結果を並列的に眺めて、
あぁAってこういう感じねと理解するのがもはや最も一般的な概念の構築方法で、私た
ちの頭自体、もはやそういう風にできていると言ってもよいだろう。さらに言えば、
Google Map/Earthは何はともあれ世界の情報をくまなく映し込んだ写像としてもはや
十分に機能している為、どこに行くにも何を食べるにも、まずはググって、その場所や
対象の何たるかをそこにどんな検索結果が並ぶかで理解し、そこへの距離やその過程で
遭遇・通過するはずの様々な事象を頭に入れ、そういうものとしてそこに向かい、そう
いうものとして対象を受容する。言い過ぎではなしに、情報が十分にはりめぐらされた
都市部においては特に、世界の半分はGoogleでできている…」
つまり筆者が前述で公共性が立ち上がるところの直接的な場として指摘した人々の視点が、そ
もそも私たちの身の回りの環境、特にその情報空間との応答の中でフィードバックループ的に
形成されているという単純な話だ。筆者が指摘するまでもなく、現代に暮らす私たちであれば
実感しない人はいないだろう。私たちを取り巻く環境、特に情報空間は、もはやコントロール
する対象というよりは、自然現象に近いものとして捉えられる感覚がより素直なところだろう
か。そして我々は、酸素を呼吸して生命活動を維持するように、それら「新しい自然現象」と
の交感の中で日々を過ごす。
こうした感覚は、「建築情報学へ」の第3章で斉藤賢爾氏が提示しているメタ・ネイチャー的
なものの見方とも重なる。同氏の掲載テキストを一部抜粋する。
「…進んだ“自動化分散社会環境”は“拡張された自然環境”と区別し難い…メタ・ネイ
チャーは、人間同士の間で生産や分配の分業を行って、財やサービスを消費するという
よりも、人間が自身の目的に沿って環境を手入れした結果、自動的に生産・分配される
財やサービスから“人間が採集できる環境”を意味し、社会のモデルは農耕・産業社会か
らむしろ狩猟採集社会へと変化する…」 (『建築情報学へ』に寄稿された、斉藤賢爾
『管理のディセントラリゼーション(分散)へ』 P.217より)
オンライン版の日本経済新聞で、「あなたの再エネ電気、私が買う 個人取引の未来を見た」
という記事を目にした。いま自分が使う電気がどこから来ているかが特定でき、電気の個人間
での取引や持続可能なエネルギー生産により生み出された電気に絞って使用するなどの選択が
ブロックチェーンの技術基盤により可能になるというものだ。ブロックチェーンが、私たち
一人ひとりの環境におけるふるまいが環境に対して働きかけるアクションでもあることに対し、
より顕著な意識付けをもたらしうる。その指摘には納得させられるものがある。そして一人ひ
とりがそうした状況に自覚的になれば、公共領域は確実に変わる。
ただし、ここで今あらためて大事なポイントに立ち戻ると、ではそのような情報空間に立ち上
がる公共の場、あるいはそこで交錯する人々視点のネットワークに対して、あらためてどうそ
こに介入するのかという最初の問いに返ってくる。エリザベス・ディラー氏がBad Pressから
スタートしたように、私たちは自分たちの日常の中のどこに介入すべきシャツの折り目を見つ
けられるのだろうか。
そんなことを考えていた折り、ギャラリーαMで3月5日まで開催されている、永田康祐氏の個
展「イート」が頭をよぎった。
ビデオエッセイの形式をとる永田氏の展示内容は、テレビ朝日による永田氏への同展に関する
インタビューに詳しい。筆者が関心をもった点は、食事という日常に埋もれた行為をあらため
て精緻に紐解き、そもそも食事とは何か、料理とは何か、ある素材が生産され、人々の口に入
り消化されるまで、食や料理にはどんな他者や道具、それらによる行為が介在しているのかを
永田氏が自身のリアルな問題として捉え直しているその実践的な態度だ。どこまでが料理で、
どこから食べる行為なのか、様々な行為者が介在する食という行為のネットワークの中に、実
感として自らに落とし前をつけられるところにいくまで、実践を惜しまないこと。小さく見え
ているごく具体的な対象に、一定の時間を注ぎ込み、向き合って、その一手一手について意味
や情報の広がりをできるだけ検証してみること。つまり概念をその構成要素に分解し、上妻
世海氏が指摘するような意味でリバースエンジニアリングすること。膨大に広がるネットワー
クの中で個人が取り組める範囲の有限性に直面しながら、その中に個別でもよいからなるべく
具体的で、シンプルな実践のガイドラインを見つけること。それらの実践は、その一つひとつ
がネットワークと付き合っていくリアルで確実な道具になるはずだ。
本コラムでは、ネットワークという概念の周縁を、随分と様々な回り道をしながら、思いのむ
くままに模索してきた。ネットワークをめぐる重要なフレームワークにも出会えた。特に「感
性の計算―世界を計算的に眺める眼差し」のコラムで紹介した伊藤亜紗氏のアプローチからは
大きな影響を受けたし、サイバネティクス的なものの見方の先にある、可能性の広がりへの見
通しも立ちつつあると感じる。そしてだからこそ、目下の関心は個人としての、ごく個人的な
視点からのネットワークへの没入というところに向かっているのだと考える。
私たちが日々面する何でもない些細なものごとには、ささやかでも必ず固有のネットワークが
付帯している。その広がりにいちいち目配せし、いかに具象的かつ身体的なレベルでそのネッ
トワークに没入していけるか。きっかけはどこにでもある。まずひとつ目に飛び込むことに尽
きるのだ。

Bad Pressのインスタレーションの一環としてデザインされたシャツ「Lapel fold with
crumpled panels」
ⒸDiller Scofidio + Renfro, Photography by Michael Moran