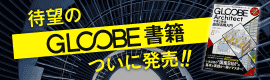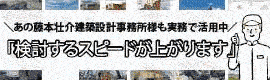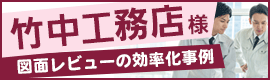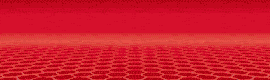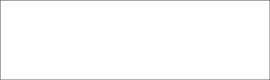![]()
ザハ・ハディドのデザイン
2016.04.05
ArchiFuture's Eye 日建設計 山梨知彦
3月31日、ザハ・ハディドが亡くなった。
朝日新聞の天声人語がその訃報に触れていたことからも、デザイナーを冷遇しがちな日本にお
いてですら、今や有名女性建築家として広く一般の人々にも知られた存在となっていたことが
わかる。
■衝撃のデビュー
しかしザハは、建築デザインの世界では、既に30年以上も前から世界的に知られた存在となっ
ていた。ザハが衝撃のデビューを果たしたのは、香港ピークのコンペ。1983年3月のことだっ
た。今から30年以上も前の話だが、以来ザハのデザインは、世界中の建築家や建築家のたまご
達を今日まで刺激し続けてきた。告白すれば、僕も学生時代に、わずか10歳年上の彼女の作品
により建築的洗礼を受けた一人だ。
1983年3月といえば、僕は大学の4年になる直前で、卒業設計のテーマを考え始めていたとこ
ろだった。
当時のザハの作風は、新国立競技場案に見られたような流動的な形状ではなく、空中に建築物
の断片を投げ込んだような、後に「脱構築的建築」と名付けられることになる、ある意味で現
在のザハよりもさらにアバンギャルドなものであった。その頃の作風は、度々「構造的配慮を
欠いた」とか「重力を無視した」といった言葉で解説されるように、描かれたドローイングの
中には、断片化された形態が浮遊した状態があるのみで、柱や梁といった構造体は見えなかっ
た。
■あらわし
ザハ自身がその時点において、構造体についてどのような考え方を持っていたのかは、わから
ない。しかしながら、構造体を露出して建築表現の一部として使う「あらわし」の伝統を持つ
国「日本」で生まれ育ち、建築教育を受けた僕には、ザハの浮遊する形体のどれもが、建築の
意匠部材であると同時に構造体にも見えた。構造体に抽象的な形状を与えることで、視覚的に
は重力から解き離された状態を生み出そうとしているに違いない、と疑いなく信じ込んでいた。
以来、「抽象化した構造体をあらわしにするだけで、建築が成立しないものだろうか」という
試みを折に触れて繰り返してきたように思う。僕自身がデザインを担当した「ホキ美術館」や
「On the water」はそんな仕事だ。
そんな建築的な洗礼を受けてしまった僕からすれば、昨今のザハが提示してきた、流動感に溢
れるクラッディング(建築の表層の仕上げ部分)を、完全に構造体とは切り離してしまった状
態で、デジタルデザインの手法を用いて精度高く実現する手法にはどこか不満を感じていた。
「これはザハが本当にやりたいことではない。デジタルデザインの手法を使って、構造体=ク
ラッディングであるような建築こそが、ザハが本当にやりたいことに違いない!」とかってに
信じ込んでいた。
■新国立競技場のキールアーチ
だから、新国立のザハ案にキールアーチの存在を見た時には、このキールアーチをきれいな
「張りぼて」としてではなく、構造体そのものでありながら、ザハが望む形へと抽象化して外
装ともしてしまうこと、さらに可能であれば同時に環境装置ともすることこそザハが望む道で
あり、突き進むべき正しい方向なのだ!と、勝手に熱くなったことを覚えている。
残念ながら、白紙撤回と今回の不幸が重なり、ザハ本人に真意をたずねることは出来なくなっ
てしまった。でも僕は、学生時代にザハから受けた洗礼をかたくなに守り、構造体や環境建築
を成立させるエレメント自体が高度に統合され「あらわし」にされつつも、存在感のある形を
同時に提示できるような建築を、デジタルデザインの手法を徹底的に使うことで実現したいと
思っている。
偉大なる建築家、ザハ・ハディドの冥福をお祈りします。

ホキ美術館

On the water