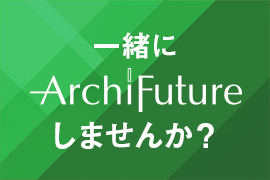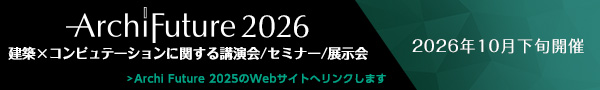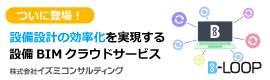![]()
新人設計研修 即戦力とスキルセット
2024.12.24
パラメトリック・ボイス 前田建設工業 綱川隆司
このコラムは飛騨出張の帰りの新幹線で書いています。飛騨市と当社で「地域資源の活用によ
る持続可能なまちづくりに関する連携協定」を今年8月に締結し、12月から始まる設計配属予
定の新人研修のテーマで飛騨古川をテーマに選び、今回はその引率役でした。飛騨市のご協力
の下、十数名の新人を受け入れていただき現地でワークショップを開催しました。
今回の研修のコンセプトはずばり「即戦力」です。どの業界でも人手不足が顕著ですが、新卒
採用の一年生にそれを期待するのはどうかと思われる向きもあるかもしれません。約10ヵ月
の集合研修を経て、来る2月に本配属になるのですが、配属先のオンジョブでの教育に割くリ
ソースは十分とは言えない状況で、インターンシップや採用面接で学生時代に見知った人もい
ますが、「これからは手取り足取りの指導は期待できないかもね」と私は新人たちを不安がら
せるようなことを言ったりもします。「即戦力」はそのためのマインドセットであり配属先の
切なる願いでもあります。今回はそんな時代に求められる建築設計者のスキルセットを考えて
みます。
今回の研修では設計の本質として、プロジェクトにおける「クライアントの要望を理解し、そ
れを計画に落とし込むスキル」を求めました。具体的な敷地を想定し、施主に相当する方に登
場いただき、その地域に対する思いと今回のプロジェクトへの期待を説明いただきました。ク
ライアントニーズを理解すること、それは顕在化したものと潜在化したものがあります。感じ
たのはそれらを受け取る力・言語化する力に個人差があるということです。
一部の大学では、実際のクライアントや実務経験を持つ教員とのロールプレイを通じて、学生
に実務に近い経験を提供していると聞きました。学生がクライアントのニーズを理解し、それ
を設計に反映させるプロセスを学べることは素晴らしいと思います。実務ではさらに、予算の
制約、法規制、施工上の制限など、多くの要素が絡み合います。これらは入社後の研修や
OJT(On-the-Job Training)を通じて体験し、プロジェクトマネジメント能力ともいえるレ
ベルまで引き上げていく必要があります。そのためには傾聴するだけでなく積極的なコミュニ
ケーションとプレゼンテーション技術が必須です。さらにはタフなネゴシエーションスキルも
期待されるでしょう。
このコラムではデジタルツールのスキルにも触れなければなりません。特にBIMについて、そ
の教育のスタートラインをどこに設定すべきか、毎回悩むところでした。今回も研修前に新人
に事前アンケートを行いました。およそ3割の受講者は「モデリングも作図もできる」、4割
が「モデリングはできるが作図はできない」、残り3割は「少しさわった程度」でした。これ
までの通説では、海外ではデジタルデザイン教育が積極的に取り入れられ、日本はそれに追随
している、と言われていました。今回7割はモデリングの経験者で、実際に採用面接や入社後
の研修を通して、Rhinocerosなどの3Dモデリングツールを使いビジュアルを作成するスキル
はここ数年で相当レベルが上がったと感じます。ところで、かつてはビジュアライズのツール
もBIMも一緒くたにされてましたが、現在はプレゼンが目的のビジュアライズ、生産が目的で
あるBIMと業務でも分けて位置付けています。ゼネコンでのデジタルデザイン教育の切り口は、
設計・施工の効率化や品質の向上を目指すことが多いので、その辺りは今後実務の中で学んで
くれることを期待しています。
しかし今現在大きな潮流になり始めているデジタルファブリケーションを考えたとき、従来の
ものづくりの延長では語れないと思うことも多いです。自動車がICE(内燃機関)からBEVに
変わるくらいのインパクトがあるのではないでしょうか。これについては我々企業側だけな
く、産学共同で国際的な潮流に沿ったデジタルファブリケーション教育を強化し、建築業界を
国際的な競争力の視点で捉える必要があると感じます。
ここまで書き進めて感じるのは、建築設計者に求められるスキルセットは多岐に渡り、技術の
進歩が加速している現代では大学院まで含めた6年間でも足りないのではないかという危惧と、
学生が自分の興味やキャリア目標に合わせた専門性を高めてきても、就職したらリセットされ
て想定外のスタートラインに立たされていないかという懸念です。
もちろん大学はゼネコンマンを養成する場ではありませんし、ましてや建築士の予備校でもあ
りません。ただし建築的な例えで恐縮ですが、どんな基礎ができているかで自ずと上部の建屋
の規模は決まってしまいます。
一方で建築設計者の職能や職域の細分化についても考えるべきでしょう。デジタルファブリ
ケーションだけでなく、サステナビリティ、AIなど、今後も関連する領域は多岐に増えていき
ます。それぞれの分野で必要な専門的な知識と技術に対応した教育プログラムを提供すること
が出来るのか、建築で足りなければ採用の枠を他学科まで広げるのか、いくつか考え方のオプ
ションはあると思います。我々はチームでプロジェクトを進めることが常であり、それぞれの
メンバーが特定の専門分野において高いスキルを持つことがプロジェクトの成否に関わること
は理解しています。
私の所属する設計戦略部を例にとれば、大規模木造物件では木質構造材や維持管理の領域、
LCAでは環境工学の領域、旧渡辺甚吉邸の運用に関していえば建築史の領域、といった様々な
専門領域の人材が増えてきました。
総じて、建築教育は、技術の進歩と業界のニーズに応じて進化し続ける必要がありますが、職
能・職域の細分化とスキルセットの定義が重要性を増しており、それには大学教育の充実も無
関係では無いと思います。教育機関と業界が連携し、新しい技術に対応できる人材を育成する
土壌が不可欠です。

写真は飛騨市での研修の1場面。古民家を改修した「FabCafe Hida」にて、株式会社 飛騨の森
でクマは踊る(通称「ヒダクマ」)の代表 岩岡様の講義の様子。