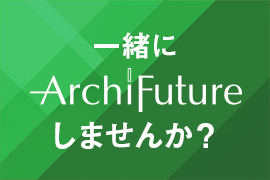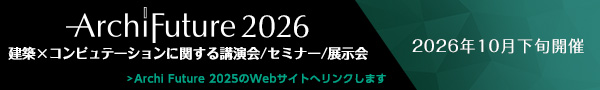![]()
データ活用は目的ではなく手段である
2024.05.14
パラメトリック・ボイス
東京大学 / スタジオノラ 谷口 景一朗
この春、学芸出版社より「情報と建築学:デジタル技術は建築をどう拡張するか/東京大学特
別講義」が刊行された。これは2022年に開催された「東京大学建築情報学シンポジウム」に
登壇した筆者を含む東京大学大学院建築学専攻の38名の研究者が寄稿した、各研究テーマと情
報との関係についての論考集である。シンポジウムの様子については、筆者のコラム「『建築
情報学』による建築学領域の横断、その第一歩」に詳述しているので参照されたい。
改めてこの書籍を読み返してみると、意匠・計画・歴史・構法・環境・構造・材料といった建
築学を構成する各分野のそれぞれの視点から建築情報学をどのように見ているのか、各研究者
のスタンスが明らかとなって非常に読み応えがある。シンポジウムのセッション名から引き継
がれた「デジタル・クリエイティビティ」、「デジタル・インタラクティビティ」、「デジタ
ル・サスティナビリティ」、「デジタル・マテリアリティ」、「デジタル・プリディクタビリ
ティ」、「デジタル・レジティマシー」という6つの章立ても秀逸で、建築学の分野構成を再構
築してくれるような、新たな視点を獲得することができる。また、それぞれに自身の研究テー
マに軸足を置いて情報学とのかかわりを論じているのに、なんとなく「複雑なものを複雑なま
ま」とか「人の振る舞い」とか「つなぐ」とかいった共通のキーワードが見えてくることも興
味深い。建築を取り巻く不確実(Uncertainty)な要素を、そのまま建築の設計・施工・運用
フェーズに取り込むという、昨今のトレンドが浮かび上がってくる。さらには、筆者のように
普段からエンジニアリングの観点より、情報学にどっぷり浸かっている方の論考よりも、普段
は情報学から距離をとっているように見える方、例えば筆者と同じセッションに登壇した岡部
明子先生の「できてきたまちの解明、わからないことのおもしろさ」や川添善行先生の「建築
という行為に内在する情報とは」といった論考の方が、個人的には新たな気づきが多い。そう
いう方が建築や都市、およびその周縁に存在するものの何を「情報」として、あるいは「デー
タ」として捉え、それらを取り扱うことで何を建築情報学に期待しているのか。そんなことが
見えてきたこともこの書籍が刊行された1つの大きな価値だろう。
ところで、春は大学の研究室にとって新しい学生を向かい入れる季節である。今年も多くの学
生が研究室の様子を伺いに訪問してくれている。筆者らの建築GX研究グループに興味を持って
くれることは大変ありがたく、彼らがどんな研究テーマに関心があるのかを聞くことは我々に
とっても新たな気づきにつながることも多い。ところがここ数年、気になる現象がある。それ
は「データを扱うことに興味がある」という志望理由を挙げる学生が一定数いることである。
おそらく先述の通り、情報学にどっぷり浸かっている筆者の研究室に所属すれば、シミュレー
ションだとか機械学習だとかの技術を使った研究に従事できると思ってくれているのであろう。
もちろん、研究手法に興味を持ってアプローチしてきてくれること自体は嬉しく思う。ただ、
やはり「データ活用」はどこまでいっても手段であって、目的ではない。データを扱った先に
どんな社会をつくりたいのか、どんな社会実装を目指すのか。ぜひそこまで考えを巡らせてみ
てほしい。「情報と建築学:デジタル技術は建築をどう拡張するか/東京大学特別講義」は、
データ活用の先に何ができるのか、そのカタログのような書籍である。学生の方にはぜひ手に
取ってもらい、情報やデータがどう社会を変えるのか、その一端を感じ取ってもらいたい。
(なお、この手段と目的の取違えはBIM活用やAI活用の議論でも頻繁に目にする光景なので、
決して学生だけの問題ではない。筆者も含めて、建築・都市に関わるすべての人が意識しなけ
ればいけない問題だと思う)
全ての道はデータから通ず。では、君はどこに向かうのか。
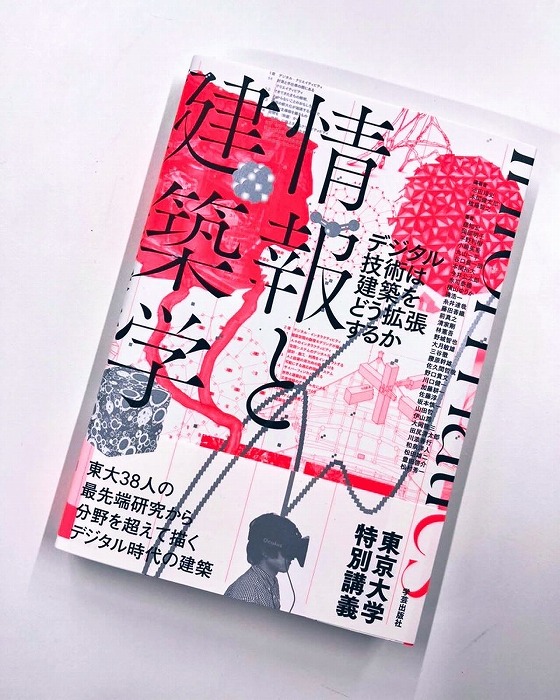
書籍「情報と建築学:デジタル技術は建築をどう拡張するか/東京大学特別講義」